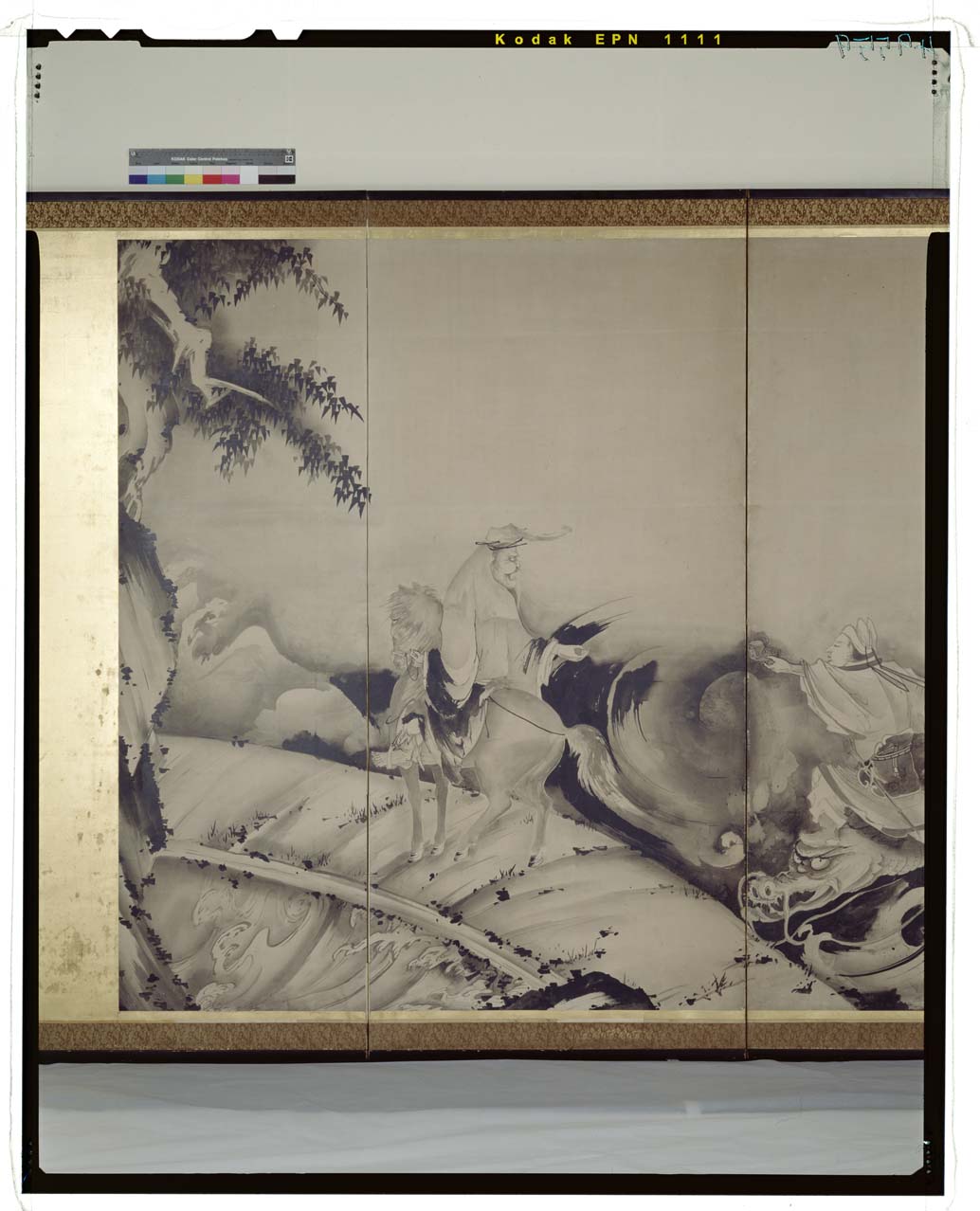清岡 公張(きよおか ともはる、1841年8月26日(天保12年7月10日) - 1901年(明治34年)2月25日)は、日本の武士(土佐藩士)、官僚。従二位勲一等子爵。通称は半四郎、号は東望。
略歴
1841年、土佐藩郷士の子弟として土佐国安芸郡田野浦に生まれる。伊勢へ遊学し、のちに上洛して諸藩の勤王の志士と交わった。文久年間に上京し、藩命により三条実美の衛士となる。八月十八日の政変による七卿落ちの際には、七卿に同行して長州藩に亡命する。禁門の変では長州藩と共に参戦するが敗北し、再び長州へ逃れている。
乾退助に脱藩を提案
慶応3年9月9日(1867年10月6日)、土佐藩お抱えの刀鍛冶・左行秀(豊永久左衛門)は、乾退助が江戸の土佐藩邸に勤王派浪士を隠匿し、薩摩藩が京都で挙兵した場合、退助らの一党が東国で挙兵する計画を立てていると、寺村左膳に対し密告を行った。行秀は乾退助が水戸浪士(もと天狗党)・中村勇吉に宛た書簡の写しを証拠として所有しており、退助の失脚を狙って左膳に密告したものである。「この事が容堂公の耳に入れば、退助の命はとても助からないであろう」という話を漏れ聞いた清岡公張(半四郎)は、退助の身を心配し土佐勤王党の一員であった島村寿太郎(武市瑞山の妻・富子の弟で、瑞山の義弟)に乾退助を脱藩させることを提案。島村が退助に面会して脱藩を勧めた。しかし、退助は容堂の御側御用役・西野友保(彦四郎)に対し、水戸浪士を藩邸に隠匿していることは、既に5月(薩土討幕の密約締結を報告の際)に自ら容堂公へ申し上げている事であるため、既に覚悟は出来ており御沙汰を俟つのみであると返答している。果たしてこれに対して容堂は、
と答えたため退助は命拾いをしたという。
維新以降
維新後は新政府に出仕し、地方官を皮切りに、1883年(明治16年)からは元老院議官や宮内省図書頭、貴族院子爵議員(1890年7月10日-1891年5月28日)などを歴任した。1887年(明治20年)には維新の功により子爵を授けられた。1890年(明治23年)10月20日、錦鶏間祗候となる。1891年(明治24年)、勲一等瑞宝章。1897年(明治30年)ロシア皇帝ニコラス戴冠式に参列後、欧米巡遊を行う。1898年(明治31年)枢密顧問官に就任する。
1901年2月、死去。享年60。墓所は、東京都文京区の護国寺。
栄典
- 明治3年5月8日 - 従五位下
- 1882年(明治15年)2月1日 - 正五位
- 1883年(明治16年)6月5日 - 従四位
- 1886年(明治19年)10月20日 - 従三位
- 1894年(明治27年)6月30日 - 正三位
- 1901年(明治34年)2月25日 - 従二位
- 勲章等
- 1882年(明治15年)8月9日 - 勲三等旭日中綬章
- 1887年(明治20年)
- 5月9日 - 子爵
- 11月25日 - 勲二等旭日重光章
- 1889年(明治22年)11月25日 - 大日本帝国憲法発布記念章
- 1890年(明治23年)7月10日 - 貴族院議員章
- 1891年(明治24年)3月30日 - 勲一等瑞宝章
- 外国勲章佩用允許
- 1896年(明治29年)10月8日 - ロシア帝国神聖アンナ第一等勲章
親族
- 父:清岡春勝 - 郷士
- 兄:清岡成章(道之助) - 長男邦之助の岳父に福沢諭吉。その長男暎一の妻は杉本鉞子の娘。
- 本人:清岡公張
- 妻:清岡覚子(歌人)沢簡徳の二女。
- 長男:清岡弥
- 二男:清岡龍(1875-1942) - 公張没時に襲爵。岳父に帝国済民会設立者・原十目吉。子に清岡繁栄。
- 三男:清岡三麿(1876-1950) - 兄没後に襲爵。専売局副参事。妻の多満は元弘前藩士・飯田巽の三女。
- 四男:清岡真彦(1879-1952) - 妻の勇子(1892年生)は出雲国造・第81代千家尊紀の娘。
- 長女:阪本新子(1880年生) - 阪本三郎の妻。
- 三女:滋野和香子(1889-1910) - 男爵・滋野清武に嫁ぐ。長女・露子をもうけた後に早世。
脚注
参考文献
- 衆議院・参議院編『議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑』大蔵省印刷局、1990年。
関連項目
- 清岡氏